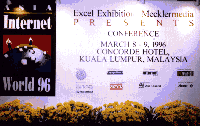 3月7日から9日にかけ、クアラルンプール市内のシャングリラ、コンコルドホテルにおいて、アジア・インターネット・ワールド'96が開催された。 JalanJalanは8、9日のコンファランスセッションに参加、ここにその概要をレポートする。各セッションへはタイトルをクリックすると行ける。しかし、1人5万円は高い。
3月7日から9日にかけ、クアラルンプール市内のシャングリラ、コンコルドホテルにおいて、アジア・インターネット・ワールド'96が開催された。 JalanJalanは8、9日のコンファランスセッションに参加、ここにその概要をレポートする。各セッションへはタイトルをクリックすると行ける。しかし、1人5万円は高い。| タイトル | 講師 | 概要 |
|---|---|---|
| アジアインターネットの将来 | トゥンク・シャリファディン博士 マレーシア電子システム研究所(MIMOS) | インターネットとはどういうものか。アジア、マレーシアの実情から将来に向けての課題など。 |
| アジアインターネット開発 | トミー・チェン博士 NetCentre社長 | ASEANにおけるインターネットブームは加熱している。これらアジアの国々がビジネス戦略のターゲットとなっている。96年、これらは顕著となる。 |
| セキュリティについて | バリー・マックイルケン セキュリティ・ダイナミック社取締役 | インターネットを取り巻く様々なセキュリティの問題。ファイアウォール、オーセンティケーション、電子署名など。 |
| コンテンツ・コントローリング | デビッド・サックス 米Pace大学助教授 ヘンリー・ステアーズ Microft Information社社長 | インターネットやWWW上に流される様々な情報、そのコンテンツ・コントロールはどうなっているのか。その将来は。 |
| 政府方針と通信規制 | マダン・ラオ 国連コミュニケーションディレクター | インターネットにより容易にアクセスできるようにするために行政や通信業者はどういう役割を果たすのか。アジアの通信業者政策は? |
| アジアインフラの行方 | ハリッシュ・ピレイ Sembawang Media社社長 | インターネットにおけるアジアでのビジネス機会を将来性あるものとするためのインフラ整備とは。 |