 |
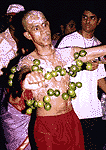 |
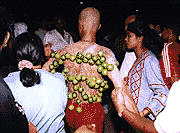 |
| 前から制御しないと 歩き続けてしまう信者。 |
体中にライムを ホックでぶら下げ、 舌を出し、 完全にイッて しまっている。 |
背中にも 盛大にライム。 |
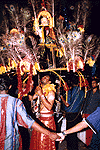 |
 |
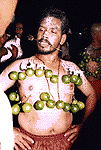 |
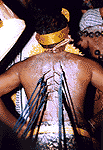 |
| 一人用飾り神輿 カバディ。 トランス状態なので この重量を支 えて踊り捲る。 |
カバディは屈強な男が ほとんど。トランス状態。 |
ライムと鉄串。 | 背中の皮膚が 盛り上がるほど 前に引っ張る。 |
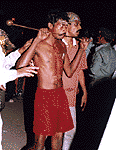 |
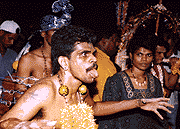 |
 |
| 極太の鉄串が 頬を貫通している。 介添人がいないと 周囲も危ない。 |
辺りを威嚇するように 咆哮を繰り返しながら歩く。 |
サトウキビで担がれた布の中には 生まれ立ての赤ちゃん。 |
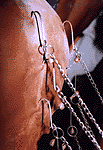 |
 |
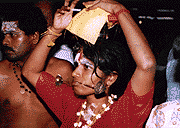 |
| 背中にホックが 食い込む。 この先に重い神輿が 繋がれる。 |
後から後から神輿の 行列はやって来る。 |
信者の苦行は老若男女、 子供にまで及ぶ。 |
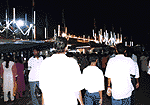 深夜2時近く、ジャラン・クチンの料金所を抜け、イポー、ペナンへ向かうハイウェイをしばらく走ると右手にバツーケーブが見えてくる。普段ならここからバツーケーブへ向けて入っていける小道があるのだが、この日は車両通行止め。ハイウェイの両側には臨時バス、観光バス、自家用車が延々と縦列駐車され、異様な光景だ。この辺りからケーブ内までは歩いて15分ほどかかるが仕方がない。
深夜2時近く、ジャラン・クチンの料金所を抜け、イポー、ペナンへ向かうハイウェイをしばらく走ると右手にバツーケーブが見えてくる。普段ならここからバツーケーブへ向けて入っていける小道があるのだが、この日は車両通行止め。ハイウェイの両側には臨時バス、観光バス、自家用車が延々と縦列駐車され、異様な光景だ。この辺りからケーブ内までは歩いて15分ほどかかるが仕方がない。 ケーブまでのホコテンは道の両脇に夜店が軒を連ね、大夜祭り状態。夜店の数は全部で690店というからものすごい。食べ物、飲み物、雑貨、お祈り用品などありとあらゆる種類の夜店がある中でやたら多くて目に付いたのが簡易床屋さんだ。左の写真がそうだが、お客さんはどこも満杯、順番待ち。こんな夜中にどういうことなんだろう、と近づいてみると、これが全員カミソリによる剃髪。
ケーブまでのホコテンは道の両脇に夜店が軒を連ね、大夜祭り状態。夜店の数は全部で690店というからものすごい。食べ物、飲み物、雑貨、お祈り用品などありとあらゆる種類の夜店がある中でやたら多くて目に付いたのが簡易床屋さんだ。左の写真がそうだが、お客さんはどこも満杯、順番待ち。こんな夜中にどういうことなんだろう、と近づいてみると、これが全員カミソリによる剃髪。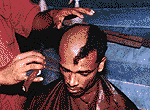 だから座って5分もするとあっという間に一丁上がりぃになってしまう。あ〜あ、そんなフサフサとした髪の毛をもったいない、と私の場合人一倍心配になってしまう。
だから座って5分もするとあっという間に一丁上がりぃになってしまう。あ〜あ、そんなフサフサとした髪の毛をもったいない、と私の場合人一倍心配になってしまう。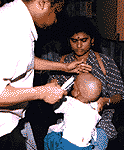 と、一応は納得しても右のような赤ん坊まで坊主になると、あ〜あ、君なんかまだ若いのにぃ、といらぬ心配をしてしまう。本当に皆さん思い切りがいいようで。それでも少年達のグループは、友達が刈られるのを見ながらみんなで大笑いしている。「おい、次お前やれよ」「いやだよぉ」等という戯れ合いをして喜んでいる。
と、一応は納得しても右のような赤ん坊まで坊主になると、あ〜あ、君なんかまだ若いのにぃ、といらぬ心配をしてしまう。本当に皆さん思い切りがいいようで。それでも少年達のグループは、友達が刈られるのを見ながらみんなで大笑いしている。「おい、次お前やれよ」「いやだよぉ」等という戯れ合いをして喜んでいる。 簡単にツルリンコにすると、今度はその頭に何やら黄色い染料の様なものを手のひらでペタペタとなで付けていく。床屋のおやじに「それはなんだ」と訊ねてみるとサンダラムと教えてくれた。これは、聖なる色黄色の化粧であり、頭を涼やかに保つ薬だということだ。お前もやって見ろと言われたが、丁重にお断り申し上げた。
簡単にツルリンコにすると、今度はその頭に何やら黄色い染料の様なものを手のひらでペタペタとなで付けていく。床屋のおやじに「それはなんだ」と訊ねてみるとサンダラムと教えてくれた。これは、聖なる色黄色の化粧であり、頭を涼やかに保つ薬だということだ。お前もやって見ろと言われたが、丁重にお断り申し上げた。 インドのお香の匂いも一段と濃くなっていく。更に進むともう自分のペースでは歩けなくなり、群衆の流れに身を任せるしかないという状態になっていく。左手の空き地には移動遊園地が開設され、深夜に子供達を乗せた観覧車はひたすら回り続ける。ものすごい喧騒と活気にたじろぐ。ビートのきいた太鼓の音があちらこちらから聞こえてくる。なんか、体が自然にノッてくる。
インドのお香の匂いも一段と濃くなっていく。更に進むともう自分のペースでは歩けなくなり、群衆の流れに身を任せるしかないという状態になっていく。左手の空き地には移動遊園地が開設され、深夜に子供達を乗せた観覧車はひたすら回り続ける。ものすごい喧騒と活気にたじろぐ。ビートのきいた太鼓の音があちらこちらから聞こえてくる。なんか、体が自然にノッてくる。 仲間、家族同士はこの揺れ動く群衆の中ではぐれないように、前の人の肩や腰につかまって移動する。右の写真がそうだが、最初この「電車ごっこ」もヒンドゥーの習わしかと思ったほどだ。
仲間、家族同士はこの揺れ動く群衆の中ではぐれないように、前の人の肩や腰につかまって移動する。右の写真がそうだが、最初この「電車ごっこ」もヒンドゥーの習わしかと思ったほどだ。 太鼓に合わせた掛け声に、叫び声が混ざり、一種異様な空間が作られていくようだ。
太鼓に合わせた掛け声に、叫び声が混ざり、一種異様な空間が作られていくようだ。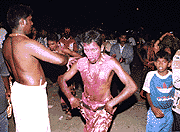 そこには体中を紅く塗り、トランス状態の目をカッと見開いて一心に歩いてくる男がいた。その背中からは十数本の縄が伸び、その端を握り締めて制御している奴がいる。口からはヨダレがだらだらと流れ落ち、前と後ろから方向を制御しないとどうなってしまうかわからないのだ。背中の縄は太く大きなフックに繋がれ、その先が背中に食い込んでいる。彼が縄を引っ張って進もうとするものだから、背中の皮膚は山のような形に引き攣れている。本来ならこの縄は重い神輿に繋がれ、それを引く苦行の信者の列となるのだろうが、正気を失った彼の縄は他の信者が引きずられるように握り締めていたのである。私はその様相の異様さに言葉を失ってしまった。はっきり言って少し恐ろしかった。
そこには体中を紅く塗り、トランス状態の目をカッと見開いて一心に歩いてくる男がいた。その背中からは十数本の縄が伸び、その端を握り締めて制御している奴がいる。口からはヨダレがだらだらと流れ落ち、前と後ろから方向を制御しないとどうなってしまうかわからないのだ。背中の縄は太く大きなフックに繋がれ、その先が背中に食い込んでいる。彼が縄を引っ張って進もうとするものだから、背中の皮膚は山のような形に引き攣れている。本来ならこの縄は重い神輿に繋がれ、それを引く苦行の信者の列となるのだろうが、正気を失った彼の縄は他の信者が引きずられるように握り締めていたのである。私はその様相の異様さに言葉を失ってしまった。はっきり言って少し恐ろしかった。 この苦行の行列、信者達はどこから沸き起こってくるのだろうか。ここでこの行列ができるまでのプロセスを紹介しよう。バツーケーブの手前に小さな川が流れている。とてもきれいとは言えない泥の川だ。深夜なので右の写真ではわからないが、暗い部分がその川だ。行列に参加する信者達はまずこの川でお清めを行う。
この苦行の行列、信者達はどこから沸き起こってくるのだろうか。ここでこの行列ができるまでのプロセスを紹介しよう。バツーケーブの手前に小さな川が流れている。とてもきれいとは言えない泥の川だ。深夜なので右の写真ではわからないが、暗い部分がその川だ。行列に参加する信者達はまずこの川でお清めを行う。

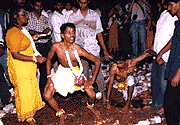
 苦行の信者達の準備が出来上がると太鼓隊のテンションも最高潮に達する。素晴らしいビートに周りの見物人達の体も自然に動いてしまうほどだ。そして全ての準備が整うと、リーダーの掛け声の下、群衆のひしめくケーブへ向かう通りへとでていくのだ。この時、介添人達は、信者達をなだめながら、制御しながら、周囲の見物人との接触がないように最大限の気を配りながら歩いていくのだ。
苦行の信者達の準備が出来上がると太鼓隊のテンションも最高潮に達する。素晴らしいビートに周りの見物人達の体も自然に動いてしまうほどだ。そして全ての準備が整うと、リーダーの掛け声の下、群衆のひしめくケーブへ向かう通りへとでていくのだ。この時、介添人達は、信者達をなだめながら、制御しながら、周囲の見物人との接触がないように最大限の気を配りながら歩いていくのだ。
 に戻る
に戻る